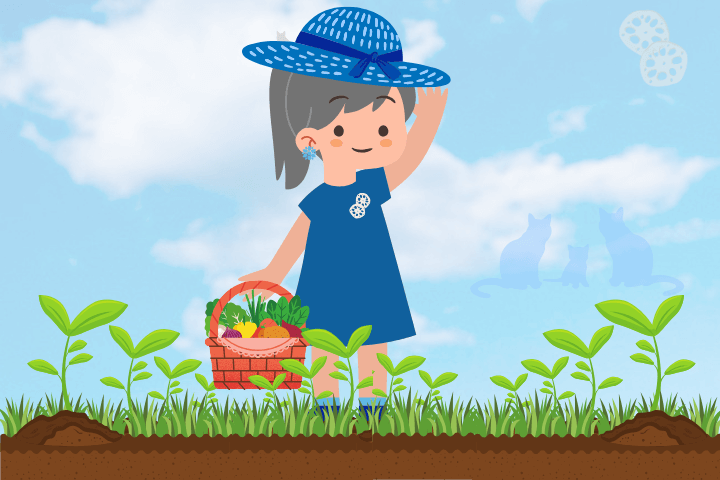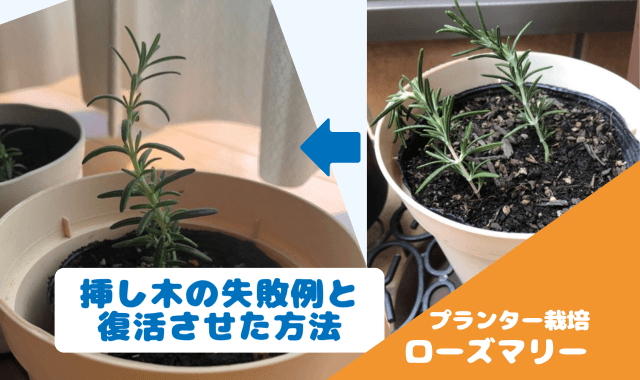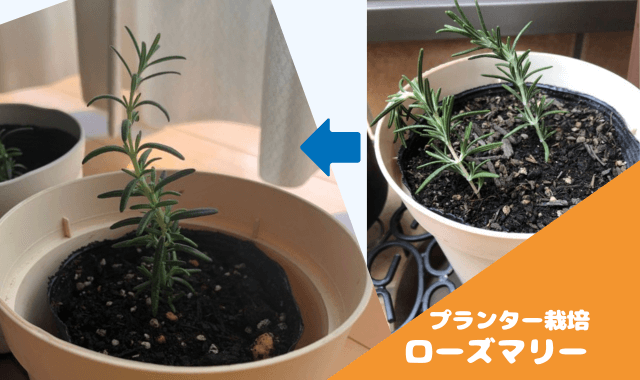
こんにちは、
ズボラさんでも楽しめる
家庭菜園ブログのくらこまです!
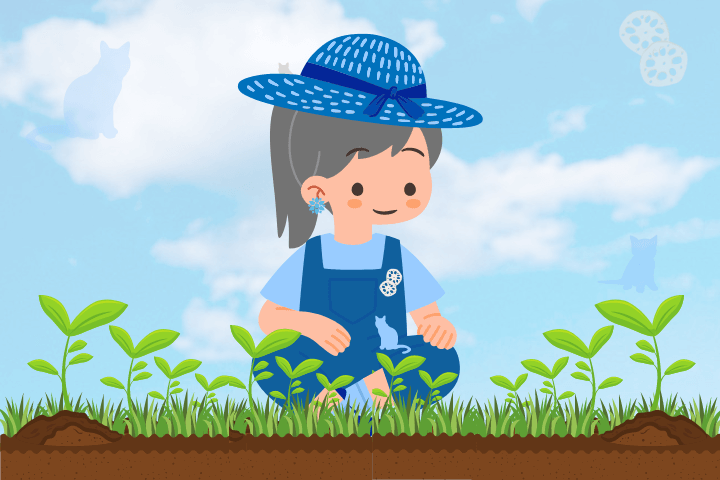
ローズマリーは、挿し木で増やすことができるハーブですが、適した時期があります。
私は、あまり考えずに寒い時期(3月)に挿し木をしてしまい、うまくいきませんでした。でも、いろいろ対策をしたことで、なんとか復活させることができました。
この記事では、ローズマリーの挿し木に失敗してしまったときの様子と、そこから復活させた方法をご紹介します。
ゆるく楽しくお読みいただけたら幸いです。
栽培の目安
| 植物名 | ローズマリー |
| 科目 | シソ科 |
| 挿し木に適した時期 | 5~6月、9~10月 |
| 手間 | ★☆☆ |
| 難易度 | ★☆☆ |
| 難易度理由 | 生命力が強く、挿し木で増やすことができます。 |
——————————————-
★が多い=手間かかる、難易度高い
☆が多い=手間少ない、育てやすい
※くらこま独自の判断です
失敗までの流れ
- 3月にローズマリーの挿し木をしました。
挿し木したのは、2本のローズマリーです。
ローズマリーの挿し木の方法については、こちらの記事をご覧ください。 - 挿し木後、寒い屋外に置いておきました。
寒い時期だけど、日が当たる場所においておけば大丈夫だろうと思い、屋外の日の当たる場所に置きました。 -
だんだんローズマリーの元気がなくなってきました。
5日後、ローズマリーの元気がなく、ぐったりしているように見えました。
土から引き抜いてみると、土に挿した部分が黒っぽくなっていて、弱っているように見えました。
この時点で、挿し木の方法が失敗していることに気づきました。
復活までに、やってみたこと
①室内に移動させ、水に挿して管理
寒さが原因かもしれないと思い、ローズマリーを室内に移動させました。
土に直接挿していたのをやめ、まずは水に挿して根を出させることにしました。
そのときに行った方法をご紹介しますね。
1本目のローズマリー
とくに傷んでいる様子がなかったため、水を入れたコップに、そのまま挿して様子を見ることにしました。
2本目のローズマリー
土に挿していた部分が黒く変色していて、かなり弱っている様子でした。そこで以下の対策をしました。
- 黒くなった部分を切り落とす。
- 下のほうの葉を摘み取る。
- 水に挿す。
このとき使った容器は、3個セットの豆腐が入っていたものです。弱っていてまっすぐ立たなかったため、斜めに傾けて容器に挿しました。
その後の様子
最初はぐったりと下を向いていましたが、少しずつ回復し、3日後には上向きになってきました。
その後は、水を入れたコップに挿し替えて育てました。
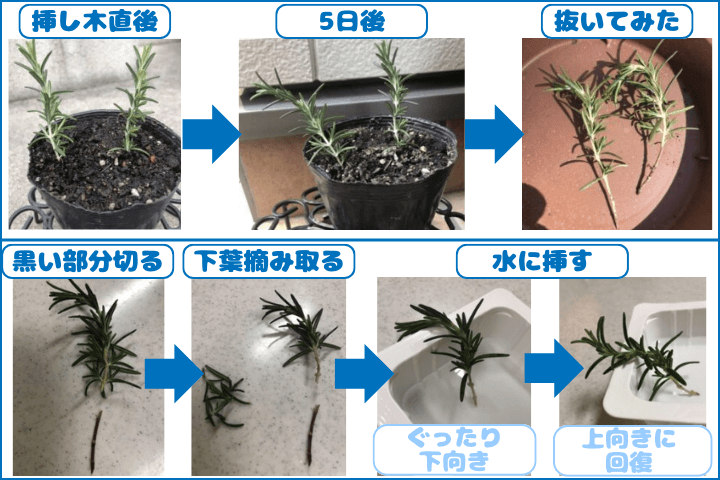
置き場所の工夫
置き場所は、日の当たる部屋の窓際にし、レースのカーテンは閉めたままで、昼間は暖房もつけていました。
②根が出たら土に植え付け(育苗ポット)
1本目のローズマリー
水に挿してから3週間後、根が出てきたので、育苗ポットに土を入れて植え付けました。使用したのは野菜用の培養土です。
※本来は「挿し木用の土」の方が適していますが、今回は手元になかったので、家にあった野菜用の培養土を使いました。
2本目のローズマリー
さらに1週間後、元気がなかったもう1本のローズマリーにも根が出てきました。
こちらは挿し木用の土を使って育苗ポットに植え付けました。
③ 暖かくなるまでは室内で管理
屋外はまだ寒かったため、根がたくさん出て元気になるまでは安心できませんでした。
そこで、暖かくなるまでは引き続き、室内の同じ場所で様子をみることにしました。
育苗ポットは、一回り大きいプランターの中に入れました。
この方法は必須ではありませんが、水はけがよくなり、管理しやすくなります。
また、夜は暖房を切っていたので、寒さ対策としても役立ちました。
④置く向きを工夫
どちらのローズマリーも少し斜めに育っていたため、傾いている方を窓とは反対側に向けて置きました。
理由
植物は太陽の方に向かって伸びようとするため、太陽の光と反対の向きに置くことで、姿勢が立ち上がってくれることを期待しました。
経過観察
1週間くらいたつと、少しずつ太陽の光を求めて、立ち上がってきました。苗もだんだん伸びてきたので順調に回復しているようでした。
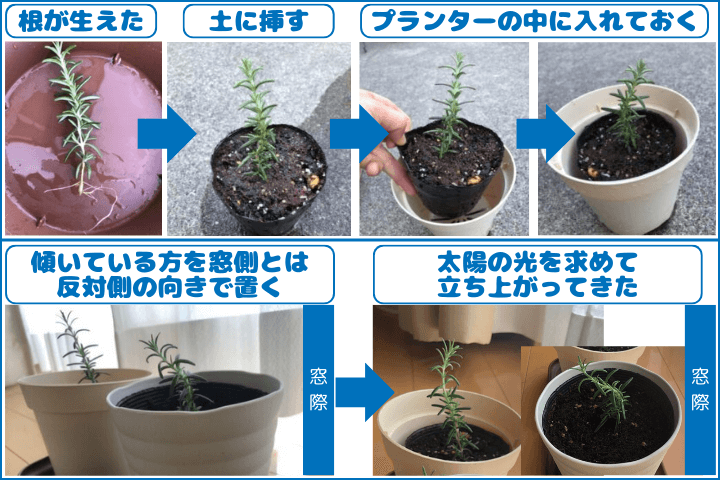
⑤プランターに植え替えて、屋外で育てる
5月になり暖かくなってきました。
ローズマリーたちも元気になってきたので、プランターに植え替えて屋外で育てることにしました。
プランターへの植え替え手順
- 人差し指と中指の間にローズマリーの茎がくるように手を添えます。
- 育苗ポットごと軽く下向きにして、苗をやさしく取り出します。
- 苗と周りの土を崩さず、そのままプランターに植え付けます。
※ローズマリーだけを引き抜いて植え付けると、枯れてしまう可能性があります。
育苗ポットの中身(土がついたまま)をそのまま植え付けてくださいね。
⑥屋外での置き場所とひと工夫?
置き場所
植替え後すぐは、屋外の日が当たりすぎないところに置いて様子をみました。
室内で育てていた苗を、いきなり日当たりの良い場所に置くと、苗に負担がかかってしまうためです。
数日後、日当たりと風通しの良い場所へ移しました。
気を付けること
ローズマリーは湿気に弱いため、じめじめした場所は避け、風通しの良い場所に置くのがポイントです。
乾燥気味の環境を好むため、水のあげすぎにも注意が必要です。
仮支柱でひと工夫?
思いつきで、割りばしを支柱代わりに立て、麻ひもで軽く固定してみました。
風や雨の影響を受けにくくなると思ったからです。
でもあとで気づいたのですが、今回のローズマリーは「匍匐性(ほふくせい)」だったようです。
このタイプは上にまっすぐ伸びるのではなく、地面を這うように育つので、支柱は必要なかったかもしれません。
いただいたものだったため、最初はどの種類か分かりませんでしたが、育てていくうちに横に広がって生長する様子を見て、匍匐性だと気づきました。
補足:ローズマリーの種類
ローズマリーには、主に次の3種類があります。
- 立性(たちせい):まっすぐ上に向かって生長するタイプ
- 匍匐性(ほふくせい):地面を這うように横に広がって生長するタイプ
- 半匍匐性(はんほふくせい):匍匐性と立性の中間で、横にも上にも伸びて生長するタイプ
経過観察
植え替えから1か月後(6月)
- 1つ目の苗:下のほうに新しい葉が増えてきて、元気に育っている様子でした。
- 2つ目の苗:全体的に元気がなく、特に上のほうの葉が枯れていました。とりあえず様子を見ることにしました。
植え替えから5か月後(10月)
- 1つ目の苗:上のほうが少し枯れていたので、思い切ってその部分を切りました。
それが良かったのかは分かりませんが、その後は元気に生長しています。
- 2つ目の苗:残念ながら、全体的に枯れてしまいました。
もしかしたら、上の葉だけが枯れていた時点で、その部分を切っていれば、回復していたかもしれません。
植え替えから8か月後(翌年1月)
1つ目の苗は、少しずつ葉が増えて、順調に育っています。
ただ、1月の寒さが心配だったので、いくつか寒さ対策をしてみました。
寒さ対策として行ったこと
- 土の上にウッドチップをのせました。
- 苗に不織布をかけました。
- その上から、はさみで適当に穴をあけた透明ビニール袋をかぶせました。
- 置き場所を、あまり風が当たらないところに移動させました。
暖かくなってきたら、不織布とビニール袋ははずし、また風通しの良い場所に戻す予定です。
植え替えから1年後(翌年5月)
今のところ、元気に育ってくれています。
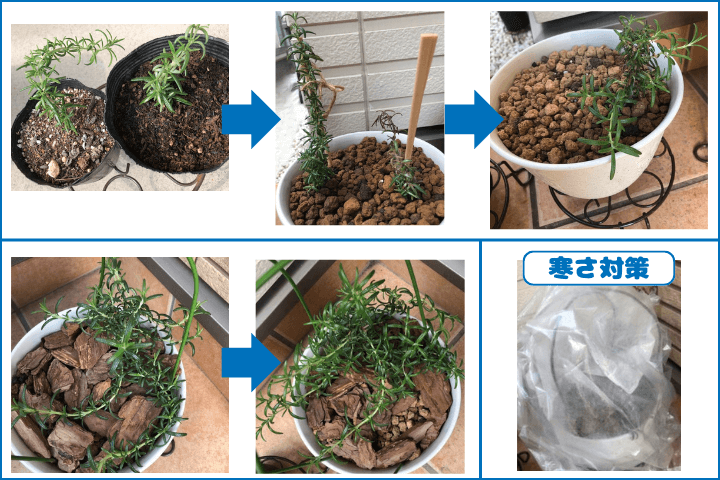
上の画像では、植え付け直後に培養土の上に赤玉土を敷いていましたが、理由ははっきり覚えていません(すみません)。
特に重要ではないと思うので、赤玉土のことはあまり気にしないでくださいね。
失敗の原因(考えられるポイント)
今回の失敗の原因は、以下が考えられます。
- 挿し木に適した時期ではなかった:ローズマリーの挿し木に適しているのは、5〜6月、9〜10月です。
今回挿し木をしたのは3月です。気温が低く、挿し木には向かない時期でした。 - 寒い場所に置いた:挿し木後すぐに寒い屋外に置いたのもよくなかったです。
まとめ
ローズマリーの挿し木は、適した時期に行うと、初心者でも成功しやすいです。
私は、なにも考えずに寒い時期に挿し木をして失敗してしまいましたが、あきらめずに対策をとったことで、なんとか元気を取り戻すことができました。
今回は2本のうち1本だけが元気に育ち、もう1本は残念ながらダメになってしまいました。
成功率100%というわけではありませんが、「ダメ元」で試してみると、意外とうまくいくこともあると感じました。
うまくいかなかったときは、この記事でご紹介した方法も、一例として、よかったら参考にしてみてくださいね。
とはいえ、復活までには手間も時間もかかるので、やはり適した時期に挿し木をするのがおすすめです。
今回はローズマリーの挿し木に失敗してしまったときの様子と、そこから復活させた方法についての記事でした。
自分で育てたものを食べると、より一層美味しく感じますよね。さらに、その生長過程にも癒されます。
ズボラさんでも楽しめる家庭菜園。
参考になれば嬉しいです。
共有の喜びと、心からの感謝を込めて、
最後までお読みいただきありがとうございました。